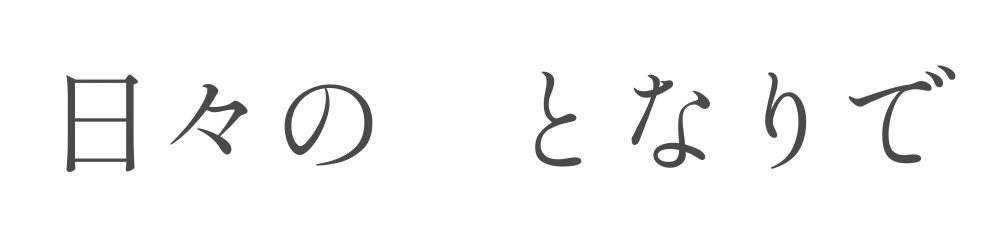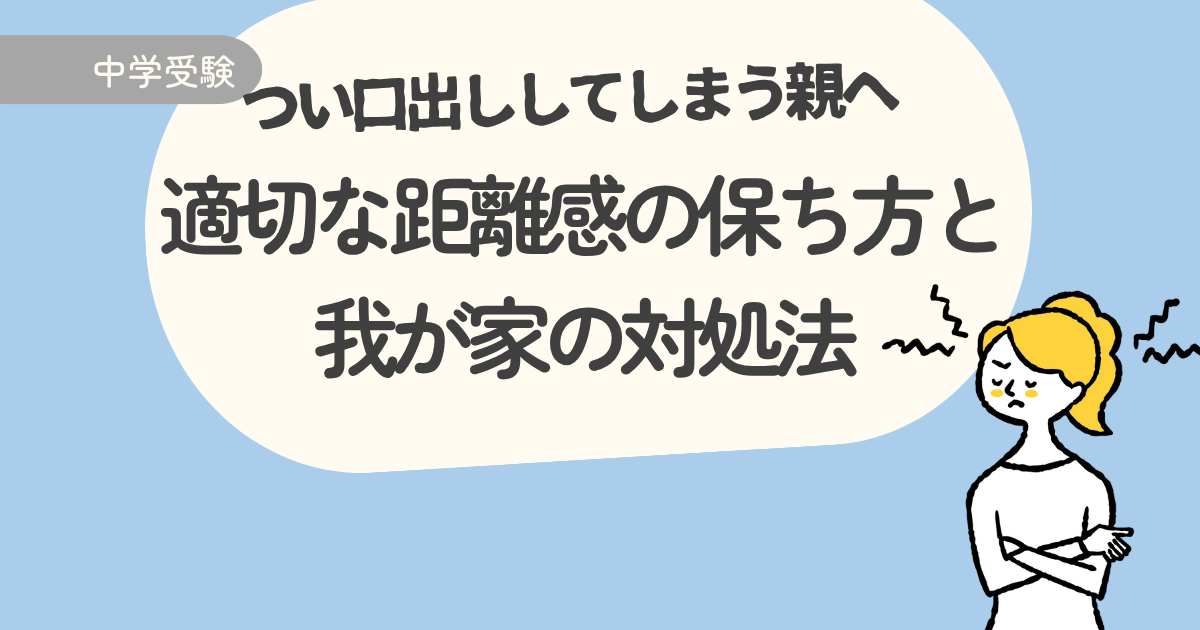中学受験に向けて子どもを応援したい——その気持ちはあっても、つい勉強に口を出しすぎてしまって「言いすぎた…」と後悔した経験はありませんか?
我が家も、小学4年生で本格的な塾通いが始まってから、親子の距離感に何度も悩まされてきました。特に勉強に関しては、「集中してるの?」「集中してないから間違えたんじゃないの?」など、余計な一言が関係をこじらせる原因になることもしばしば。
この記事では、親としての気持ちと、子どもの心の発達段階をふまえた関わり方、そして我が家の具体的な対処法をご紹介します。
つい口出ししてしまう親心と、子どもの心理的発達

まず知っておきたいのは、「子どもは親の感情をとても敏感に察知する」ということ。小学校中学年から高学年の子どもは“自我意識”が急速に発達し、他者からどう見られているかを強く意識するようになります。
この時期の子どもにとって、親の口出しは「信じてもらえていない」「監視されている」と感じさせてしまうことがあるのです。たとえ善意であっても、否定されたような印象を与えてしまえば、やる気や自己肯定感が下がるリスクがあります。
逆に言えば、この時期の子どもは「信頼されている」と感じると、大きな安心感を持って自立に向かうことができます。
我が家の原則|口出ししすぎたら“謝ってリセット”
中学受験は親子ともにストレスの多い挑戦。つい感情的に言ってしまった——そんなとき、我が家では「素直に謝って、気持ちをリセットする」ことを大事にしています。
ある日、算数のミスが続いた息子に「ちゃんと見直ししてるの!?」と強く言ってしまいました。息子は黙って下を向いたまま。その日の夜、「さっきは言い方がキツかったね、ごめんね」と伝えると、少し泣きながら「がんばってるのに…」と本音を話してくれました。
そこから、「どういう声かけだったらやる気が出る?」「アドバイスしてもいいときは教えてね」と、子ども自身にルールを決めてもらうようにしました。
言いそうになったら“物理的に離れる”のがコツ

もうひとつ大事にしているのが、「口を出しそうになったら、その場から離れる」こと。感情が高ぶったまま関わるのではなく、5分でも距離を取ると冷静になれます。
- キッチンに立って夕食の準備に集中する
- リビングではイヤホンで音楽を聴いて“耳を閉じる”
- 洗濯物をたたみながら様子だけ見る
このように「見守る姿勢」を保ちながら、つい干渉したくなる気持ちを切り替える習慣ができてきました。
どうしても冷静になれない時の一番のおすすめは、赤ちゃんの頃の動画を見ること。
10年前まで、寝返りしたことで喜んでいたじゃない。ごはん食べられて喜んでいたじゃない。
可愛い我が子の動画を見ると途端に落ち着きます。

生きているだけで十分。中学受験にチャレンジしているだけで偉い。
「手を出さない」のではなく「任せる」ことが信頼
10〜12歳は“自立の準備段階”に当たります。自分で決めたことに対して責任を持ち、成功や失敗を通して自己効力感(自分にはできるという感覚)を育んでいく時期。
この時期の子どもにとって「任されている」「自分でやっていいんだ」と感じることは、大きな力になります。だからこそ、親は“指示”ではなく“提案”や“相談”という形で関わるほうが、受け入れられやすくなります。
たとえば、「このプリント、今日のうちに終わらせたほうがいいんじゃない?」ではなく、「このプリント、いつやる予定?お母さんも予定立てたいから教えてくれる?」という言い方に変えるだけで、ぐっと空気がやわらぎました。
「戦略的ほったらかし」で自立を促すという考え方
とはいえ、「子どもに任せる」「干渉しすぎない」と言われても、実際にどこまで任せていいのか迷ってしまう親御さんも多いのではないでしょうか。
私もマイペースな息子ぴのくんには、わかっていても毎日毎日口出しをしてしまう日々。
子どもに自立した人になってほしいと、親ならみんな願うこと。
でも、口出ししないといつまでも始まらないし終わらない!
そんなときに出会って、私自身の意識を大きく変えてくれたのが、岩田かおりさんの著書『自分から学べる子になる 戦略的“ほったらかし”教育』です。
タイトルだけ見ると、「ほったらかしって大丈夫なの!?」と思うかもしれませんが、実際には“放任”とは全く異なる、戦略的に「任せていく」関わり方が丁寧に紹介されています。
特に印象的だったのは、「子どもが自分で考える機会を奪ってしまっているのは、親の“よかれと思った声かけ”かもしれない」という指摘。まさに自分のことだとハッとさせられました。
本書では、学習だけでなく、生活習慣や人間関係も含めて、子どもが自分で選び、自分で責任を持つ力を育てるためのステップが実例付きで紹介されています。忙しい日々の中でも読みやすく、実践しやすいヒントが満載です。
「うちの子、やる気がなくて…」「つい口を出してしまう」という方には、ぜひ一度読んでみてほしい1冊です。
まとめ|親も“完璧じゃない”を見せていい
中学受験は親子で挑む長丁場。親だって、つい言いすぎることもあります。それでも、「ごめんね」と伝えること、「信じてるよ」と見守ることは、何度でもできます。
親が失敗を認める姿は、子どもにとっても「完璧じゃなくていいんだ」と思える安心材料になります。そして、家の中が安全基地であり続けることが、子どもの伸びる力を支えてくれると感じています。
口出ししすぎた日も、信頼を取り戻せる日。そんな視点を持ちながら、今日も親子で受験期を歩んでいます。